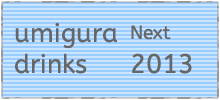どこか懐かしさを感じる空気。心地よいざわめき。
あたたかみあふれる商店街の店に、ほころんだ表情で足をとめる人たち。
小町通りを歩いていると、海老名から来たわたしでも心地よく人波にとけこんでいるのを感じる。
桜庭一樹『荒野ー12歳 ぼくの小さな黒猫ちゃん—』は、わたしが小町通りのカフェで、ゆっくりページをめくりたくなる本だ。
荒野は12歳の少女。鎌倉の古いお屋敷で、小説家の父・正慶と暮らしている。
中学校入学式の朝、北鎌倉駅を発つ電車に急いで飛びのったとき、セーラーの襟を扉にはさまれてしまった。
こまっている荒野に、銀縁メガネをかけた少年・悠也が手をさしのべる。
悠也がポケットに入れていた文庫本は五木寛之『青年は荒野をめざす』だったー。
みんな「少女の季節」があった。
しかし、大人になるとそれはだんだんと輪郭がぼやけ、触れることができなくなってしまう。
この本はそんな「少女の季節」を、小町通りの小物たちとともに、わたしの中にきらきらと蘇らせてくれる。
アンティーク着物で街を歩くアルバイト。
黒髪にさす、つやつや美味しそうなかんざし。
学校帰りのうさぎ饅頭と抹茶のお店。
なにも分からないまま、でもたしかにプチプチを音をたてはじめる「恋」の感情。
荒野がみた小町通りは、どんな色と光であふれていたのだろうか。
通りを歩きながら、そっとセーラー服を着た荒野の姿を探す。
そうすると、まだ自分のなかにいる「少女」がスキップを始めそうになるのを感じるのだ。
長尾美奈子